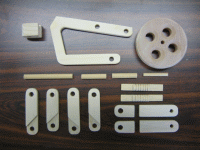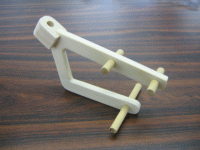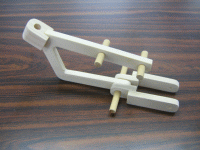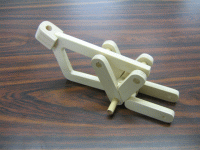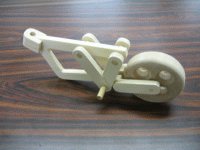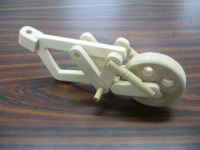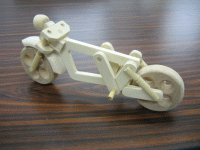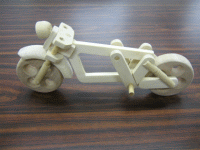▼ 製作日記(その8))
木工製作
(2)フレーム・後輪部分の製作
今回はフレームおよび後輪部分の製作に入ります。
まずは、フレームの製作について、前回使用した自在のこ?を部分的に使用しながら、板材から切り出します。 切り出し後、恒例となりましたヤスリとサンドペーパーで仕上げます。 今回は部品点数が多いので、いかに楽に作業するかが個人的なポイントでした。
その後、こまごまとした部品を作製していき、最終的に図60に示すような部品用意します。
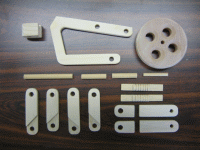
図60
それでは少しずつ組み立てていきましょう。
まず、メインフレームとステアリングを結合する軸受けを接着します。 次にサイドの補助フレームをつなぐロッド等を通します(図61参照)。 さらに、後輪を支えるためのアームをアセンブリします(図62参照)。
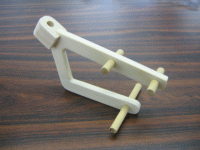 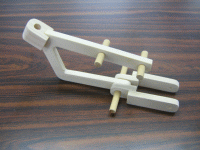
図61 図62
次に、サイドフレームを取り付けていきますが、ここで、問題発生!!。 図62では、アームの構成部品において、タイヤの軸を通す方の部品をみると、軸穴反対方向のエッジが角Rの処理をせずそのままの状態でした。 設計では角Rの処理をしておりましたが、加工を忘れておりました(汗)。その結果、サイドフレームと干渉し、意図した組み立てができないことが判明しました。
既に接着しており、ハンドルーター等で加工を試みましたが、あえなく失敗・・・。 結局、アームの部分については最初から部品を再製作することになりました。
気をとりなおして部品製作後、ようやくアセンブリまで行ったものが図63です。 ここから、さらにタイヤを取り付けたものが図64です。
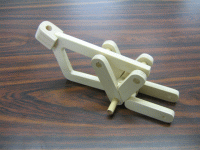 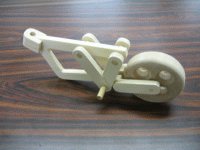
図63 図64
タイヤもよく回るようです。 後輪部最後に、クッション用のダンパー?を接着します(図65参照)。 ここまできたら、前回の前輪部と合体してみましょう(図66参照)。
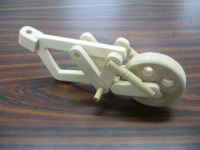 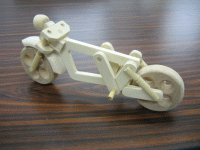
図65 図66
ぉおおー 立ちました!! まだまだ途中段階ですがかなり感動です。
いくつかの方向から見てみましょう。
 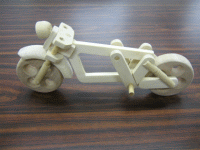
タイヤのエッジ処理(角R)の程度を設計より小さくしていたので、タイヤの接地面(平面部)が大きく、静かに置けばスタンド無しでも立つようです。 また、上手に押し出してやるとスーッとよくタイヤが転んで進みます。
さあ、つぎはエンジン部・タンク他の製作に入ります。つづく・・・。(2005/07/17)
|
【あなたの年収3倍にします!〜失敗したら商品代金+3万円払ちゃう非常識なプロジェクト】
なぜ、私が24歳で月収2000万の、【 幸せなお金持ち 】になれたのか?

私の年収を100倍以上にし、ワクワクの人生をもたらした、500以上の秘訣・ノウハウ

資格取得やスキルアップ、キャリアアップに!
自分に合った資格を探せるスクールジョブ

|